普通免許で運転できるトラックは何トンまで?サイズ・積載量を徹底解説

トラックを運転するためには免許の区分が大きなポイントになります。
特に「普通免許で運転できるトラックは何トンまで?」という疑問は、引越しや配送、農業や建設業などでトラックを使う人にとって重要なテーマです。
実は、普通免許で運転できる範囲は車両総重量や最大積載量の制限によって明確に区切られています。
また、2007年や2017年の免許制度改正によって「中型免許」「準中型免許」が新設され、取得時期によって運転可能なトラックの範囲も異なるため注意が必要です。
この記事では、普通免許で運転できるトラックの基本ルールから、実際に乗れるトラックのサイズや種類、免許制度改正の影響、仕事での活用例までを整理して解説します。
これから免許を取得する方や、業務でトラックを使いたい方に役立つ情報をわかりやすくまとめました。
目次
普通免許で運転できるトラックの基本ルール

「普通免許で運転できるトラックはどのくらいの大きさまで?」という疑問を持つ方は少なくありません。
普段の移動に使う乗用車と違い、トラックには車両総重量・最大積載量・乗車定員といった制限があり、免許の種類によって運転できる範囲が明確に定められています。
ここでは、普通免許で運転可能なトラックの条件を整理し、準中型免許・中型免許との違いを分かりやすく解説します。
普通免許で運転できる車両の条件とは
普通免許で運転できるのは、次の条件を満たした車両です。
- 車両総重量 – 3.5トン未満
- 最大積載量 – 2トン未満
- 乗車定員 – 10人以下
つまり、軽トラックや小型トラックが普通免許の範囲に収まります。
宅配や小規模な引越しでよく使われる1.5トン車や2トントラック(小型限定)も条件を満たせば普通免許で運転可能です。
ただし、積載量や車両総重量が少しでも上限を超えると準中型免許が必要になるため、車検証でしっかり確認する必要があります。
最大積載量と車両総重量の制限
「何トンまで乗れるか」を考えるときに重要なのが、車両総重量と最大積載量の違いです。
- 車両総重量 – 車両本体の重量+乗員+最大積載量を合わせた総重量
- 最大積載量 – 荷台に積める荷物の重さ
普通免許で運転できるのは「車両総重量3.5トン未満」「最大積載量2トン未満」です。
例えば、荷台が広くても積載量が2トンを超えるトラックは普通免許では運転できません。
配送業などで使う際には、荷物の重さも含めて制限を超えないよう注意が必要です。
普通免許と準中型免許・中型免許との違い
トラックを運転するうえでよく混同されるのが、普通免許・準中型免許・中型免許の違いです。
- 普通免許 – 車両総重量3.5トン未満/最大積載量2トン未満
- 準中型免許 – 車両総重量7.5トン未満/最大積載量4.5トン未満
- 中型免許 – 車両総重量11トン未満/最大積載量6.5トン未満
準中型免許が新設されたのは2017年。
これにより普通免許で運転できる範囲がより小型車両に限定されました。
以前に普通免許を取得した人(2017年3月12日以前)は「5トン未満の限定付き中型車」を運転できる場合があり、取得時期によって条件が変わるため注意が必要です。
▷普通免許の範囲を正しく理解することが重要
普通免許で運転できるトラックは小型〜2トン未満までに限られます。
- 車両総重量3.5トン未満
- 最大積載量2トン未満
- 乗車定員10人以下
この条件を超えると準中型や中型免許が必要になります。
仕事や生活でトラックを使う際には、必ず免許区分と車両の条件を照らし合わせ、自分が合法的に運転できる範囲を理解しておきましょう。
普通免許で乗れるトラックの種類とサイズ
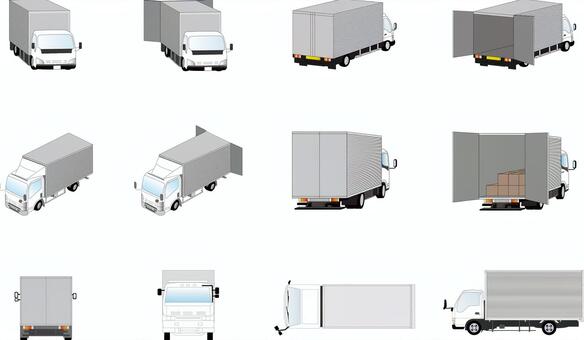
「普通免許でどの種類のトラックまで運転できるの?」という疑問は、配送や引越しの仕事に関心がある人や日常的に軽トラを使う人にとって重要なテーマです。
トラックと一口にいっても、軽トラック・小型トラック・2トントラックなど用途やサイズによって区分があり、免許条件を正しく理解しておく必要があります。
ここでは、普通免許で運転できるトラックの種類とサイズ感について整理して解説します。
2トントラックは運転できる?
結論から言えば、すべての2トントラックを普通免許で運転できるわけではありません。
普通免許で運転可能なのは、最大積載量が2トン未満・車両総重量が3.5トン未満の車両に限られます。
- 2トン車の中でも「小型トラック」と呼ばれるタイプは、積載量が1.5トン〜2トン未満に収まるため普通免許で運転可能。
- 一方で、積載量2トン以上の標準的な2トントラックや車両総重量が重い車種は、準中型免許が必要です。
そのため「2トントラック=普通免許で乗れる」とは限らない点に注意が必要です。車検証に記載されている数値を必ず確認しましょう。
軽トラック・小型トラックの特徴
軽トラック(軽トラ)は、普通免許で安心して運転できる最小サイズのトラックです。
- 車両総重量 – 約1トン前後
- 最大積載量 – 350kg
- 車両寸法 – 全長3.4m、全幅1.48m、全高2.0m以内(軽自動車規格)
農業や建築現場、引越しや宅配など幅広い場面で活躍しており、小回りの良さと維持費の安さが魅力です。
小型トラックは、軽トラよりも大きいが準中型以下に収まる車両を指します。
たとえば、最大積載量が1〜2トン未満のトラックが該当し、宅配便の集配や小規模配送でよく使われます。
荷台が広く、家具や家電を積めるため実用性が高い一方で、狭い道では運転に注意が必要です。
宅配・引越しに使われるトラックのサイズ感
宅配や引越し業務でよく使われるのは、小型〜2トントラックです。
- 宅配便(小規模配送) – 1.5トン車や小型トラックが中心。住宅街の細い道でも対応しやすく、積載量と取り回しのバランスが取れています。
- 単身引越し – 軽トラ〜1.5トン車が多く利用されます。ベッドや冷蔵庫などの大物家具も積めるサイズ感です。
- 家族引越しや大型荷物配送 – 2トントラック(標準サイズ)が主流。ただし多くは準中型免許が必要となるため、普通免許では運転できないケースが多いです。
つまり、日常的な配送や小規模引越しであれば普通免許で十分対応可能ですが、本格的な引越しや業務利用では準中型以上の免許が求められる場合があります。
▷普通免許で運転できるのは小型中心
普通免許で運転できるトラックは、軽トラックや一部の小型トラックまでに限定されます。
- 2トントラックは「積載量2トン未満」であれば運転可能
- 軽トラや小型トラックは普通免許で問題なく利用可能
- 宅配・引越しなどの小規模業務は普通免許で対応できるが、大型作業には準中型免許が必要
利用目的に合わせて、どのトラックが普通免許の範囲に収まるのかを確認しておくことが大切です。
免許制度改正とトラック運転の関係

普通免許で運転できるトラックの範囲は、免許制度の改正によって大きく変化してきました。
2007年には「中型免許」が新設され、2017年にはさらに「準中型免許」が追加されるなど、制度が段階的に細分化されています。
これにより、同じ「普通免許」でも取得時期によって運転できるトラックの範囲が異なります。
ここでは、2007年と2017年の改正内容と、その影響について整理します。
2007年の改正で変わった「中型免許」の扱い
2007年6月の道路交通法改正により、それまで「普通免許」で運転できていた車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満のトラックは、中型免許が必要となりました。
- 改正前 – 普通免許で「4トン車」と呼ばれるトラックまで運転可能
- 改正後 – 普通免許の範囲は「車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満」に縮小
この結果、物流業界では「普通免許ドライバー不足」が深刻化し、求人条件の見直しが行われました。
一方で、2007年6月1日以前に普通免許を取得していた人には「中型免許(8トン限定)」が付与され、従来どおり4トントラックまで運転可能となっています。
2017年の「準中型免許」新設の背景
2017年3月には、新たに準中型免許が創設されました。
背景には、物流業界の慢性的な人手不足と若年層ドライバー不足がありました。
- 準中型免許の範囲 – 車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満
- 取得可能年齢 – 18歳から(中型免許は20歳以上かつ経験2年以上が条件)
これにより、高校卒業直後でも比較的大きなトラックを運転できるようになり、若手ドライバーの育成を後押ししました。
改正前に免許を取得した人の運転可能範囲
免許を取得した時期によって、運転できるトラックの範囲は次のように異なります。
- 2007年6月1日以前に普通免許取得
→ 中型免許(8トン限定)が自動付与され、4トントラックまで運転可能 - 2007年6月2日〜2017年3月11日に普通免許取得
→ 車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満に制限(小型トラックまで) - 2017年3月12日以降に普通免許取得
→ 同上(3.5トン未満・2トン未満)、ただし準中型免許を取得すればより大きな車両も運転可能
このように、「自分の免許で何トンまで運転できるか」は取得時期に左右されるため、車検証や免許条件を必ず確認する必要があります。
▷免許改正を正しく理解して安全運転を
普通免許で運転できるトラックの範囲は、2007年と2017年の制度改正で大きく縮小されました。
- 2007年 – 中型免許が新設され、普通免許で乗れる車両は小型中心に限定
- 2017年 – 準中型免許が新設され、若手ドライバーでも大きなトラックを運転可能に
- 取得時期によって運転可能範囲が異なるため要確認
物流業界で働く人や業務でトラックを使う人は、こうした制度の違いを理解して免許取得や更新を計画することが重要です。
普通免許でトラックを運転する際の注意点

普通免許でトラックを運転できるとはいえ、乗用車と比べてサイズや重量が大きい分、注意すべきポイントも多く存在します。
特に業務利用では法規制や安全対策を守らなければ、事故や違反につながる可能性があります。
ここでは、積載制限や安全運転のコツ、そして業務でのルールについて整理します。
積載オーバーと道路交通法違反のリスク
トラックを運転する際に最も重要なのが積載量の管理です。
普通免許で運転可能な車両は、車両総重量や最大積載量に上限があります。
- 車両総重量 – 3.5トン未満
- 最大積載量 – 2トン未満
この範囲を超えて積載した場合、道路交通法違反となり、反則金や点数の加算が科されます。
また、積載オーバーは制動距離の増加・横転リスク・落下事故につながるため、重大事故の原因となりかねません。
荷物を積む際は必ず重量を確認し、必要であれば「制限外積載許可」を申請することも検討しましょう。
安全運転のための車両感覚と死角対策
トラックは乗用車に比べて車体が長く、幅も広いため、車両感覚の違いに慣れる必要があります。
特に注意すべきなのは以下の点です。
- 左折・右折時の内輪差 – 歩行者や自転車の巻き込み事故を防ぐため、大回りを意識する。
- 後方視界の死角 – ミラーや補助カメラを活用して確認する。
- 車両重量による制動距離の延び – 前方との車間距離を広く取る。
これらを徹底しないと、接触事故や追突事故につながります。
トラック運転に慣れていない普通免許ドライバーは、実際に業務で運転する前に研修や同乗指導を受けることが望ましいでしょう。
就業・業務利用時に注意すべきルール
普通免許で運転する場合でも、業務でトラックを使用するなら労働基準法や運輸規制の範囲を守らなければなりません。
- 労働時間規制 – ドライバーは長時間労働になりやすいため、休憩や拘束時間の上限を順守する必要がある。
- 車両管理 – 点検整備を怠ると会社・運転者双方に責任が及ぶ。
- 雇用契約上の条件確認 – 業務内容が免許条件を超える場合、事故発生時に重大なトラブルにつながる。
つまり、単に「普通免許で乗れる範囲だから大丈夫」と考えるのではなく、業務利用時のルールと責任を十分理解することが欠かせません。
▷普通免許でも安全運転と法令順守が必須
普通免許でトラックを運転できる範囲は限られていますが、積載量の超過防止・車両感覚の習得・業務ルールの順守が安全運転のカギとなります。
特に仕事で使用する場合は、会社の指導や法令を守る姿勢が不可欠です。
普通免許の範囲内でも責任は重いため、事前準備と安全意識を徹底しましょう。
就職・仕事で使える普通免許トラックの活用例

普通免許で運転できるトラックは、限られた範囲でありながらも、就職や副業、地域での仕事に幅広く活用できる存在です。
配送業や建設業、農業の現場では、軽トラックや小型トラックが欠かせない働き手となっています。
ここでは、具体的な活用例を挙げながら、普通免許がキャリアにどう役立つのかを解説します。
配送ドライバーとしての採用条件
宅配便や小規模な配送サービスでは、普通免許で運転できる1.5トン~2トン未満の小型トラックが多く活躍しています。
特に宅配業者・引越し業者・ネット通販の配送ドライバーでは、普通免許で応募できる求人が多く存在します。
採用条件では、「普通免許取得後1年以上」などの実務経験条件が付く場合もありますが、中型免許までは不要なことが多く、就職のハードルは比較的低いのが特徴です。
建設業や農業での軽トラ・小型トラック活用
農業や建設業では、軽トラックは欠かせない存在です。
- 農業分野 – 収穫物の運搬や肥料・資材の輸送
- 建設分野 – 資材や工具の現場搬入、小回りの利く現場用車両
どちらの業種も普通免許で運転可能な軽トラ・小型トラックが主力であり、即戦力として求められる場面が非常に多いのが特徴です。
地域によっては、農協や地元建設会社で普通免許ドライバーを積極的に採用しているケースもあります。
免許取得とキャリア形成のステップ
普通免許でできる仕事からスタートし、準中型免許や中型免許へのステップアップを目指すことで、より大型の車両を扱えるようになり、キャリアの幅が広がります。
- 普通免許 → 軽トラ・小型トラックでの実務経験
- 準中型免許 → 2トン以上~4.5トン未満の車両を運転可能
- 中型免許 → 大型配送や建設資材輸送の現場へ進出
このように、普通免許は物流や建設業へのキャリア形成の入り口となります。
最初の一歩として十分価値があり、その後の資格取得と経験によって安定した職に就ける可能性が高まります。
▷普通免許でも仕事の幅は広がる
普通免許で運転できるトラックは軽トラや小型トラックに限られますが、配送業・農業・建設業など多くの業種で活躍の場があることは大きな強みです。
また、ここからキャリアを広げていくためのステップとしても重要な役割を果たします。
「まずは普通免許でできる仕事から始める」ことは、トラックドライバーとしての第一歩となり、将来的なキャリアアップにもつながります。
これから免許を取得・更新する人が知っておくべきポイント

トラックを運転する上で「自分の免許でどこまで運転できるのか」を正しく理解することは非常に重要です。
特に免許制度は2007年と2017年に大きな改正があり、取得した時期によって運転できる車両の範囲が異なるため、混乱しやすいポイントでもあります。
これから免許を取得する人や、更新のタイミングを迎える人に向けて、確認すべき注意点を整理します。
自分の免許区分で運転できるトラックの確認方法
普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許には、それぞれ運転可能な車両総重量・最大積載量・乗車定員の基準が設けられています。
- 例えば、現在の普通免許で運転できるのは「車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満」のトラックです。
- 2007年以前に普通免許を取得した人は、旧制度により車両総重量8トン未満まで運転可能な場合があります。
免許証の裏面や公安委員会発行の一覧表で、自分の免許区分がどの基準に該当するかを確認しておくことが大切です。
仕事で使うなら「準中型免許」取得が有利なケース
配送業や建設業などでは、2トン以上の小型〜中型トラックを扱う機会が多くあります。
普通免許の範囲では積載量に限界があるため、業務利用を前提にするなら「準中型免許」取得が有利です。
- 準中型免許では「車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満」のトラックを運転可能
- 宅配業者や建設会社の求人条件で「準中型以上」と指定されることも増えている
将来的に物流・建築系の職種に進みたい人にとって、準中型免許を早めに取得しておくことは大きな武器になります。
普通免許で乗れる範囲を最大限活用するコツ
一方で、普通免許だけでも十分に活躍できる場面は多くあります。
- 宅配・引越し業務 – 軽トラや1.5トントラックを使用
- 農業・建設業の現場 – 軽トラでの資材・農作物の運搬
- 地域の配送・便利屋業務 – 小回りが利く小型トラックが重宝される
また、軽トラや小型トラックは燃費も良く、維持費も抑えられるため、副業や個人事業主としてスタートする場合にも相性が良いのがメリットです。
▷免許区分を理解し、目的に応じた選択を
免許制度の改正によって、普通免許で運転できる範囲は年々狭まっています。
そのため、自分の免許区分を正しく理解することが第一歩です。
- 現在の普通免許 → 軽トラ・小型トラックでの仕事が中心
- 業務で活躍の幅を広げたい → 準中型免許の取得が有利
- 普通免許だけでも十分に活かせる場面も多い
これから免許を取得・更新する人は、自分のキャリアプランに合った免許取得・活用方法を選ぶことが成功のカギとなります。
まとめ|普通免許で運転できるトラックを正しく理解して安全に活用しよう

普通免許で運転できるトラックは、最大積載量2トン未満・車両総重量3.5トン未満に制限されており、軽トラックや一部の小型トラックが対象となります。
宅配や小規模な引越し、農業や建設業など、幅広い現場で日常的に利用されることが多い車両です。
ただし、2007年・2017年の免許制度改正により、取得した時期によって運転可能なトラックの範囲が異なります。
そのため、自分の免許証がどの区分に該当するかを確認することが不可欠です。
業務でトラックを運転する予定がある場合は、準中型免許や中型免許を取得することで仕事の幅が広がるでしょう。
また、積載オーバーや法規制違反は重大なリスクを伴います。
積荷の重量やバランスの管理、車両感覚を意識した安全運転を徹底することが重要です。
これから免許を取得・更新する人は、自分のライフスタイルや仕事に必要な用途を踏まえて、最適な免許区分を選ぶことがポイントです。
普通免許で運転できる範囲を理解し、必要に応じてステップアップすることで、安全かつ効率的にトラックを活用できるでしょう。





