モーダルシフトとは?意味・背景・メリットをわかりやすく解説!

物流業界で今、避けて通れないキーワードとなっているのが「モーダルシフト」です。
これは、トラック輸送を中心とした従来の物流のあり方から、鉄道や船舶など、環境負荷の少ない輸送手段に切り替える取り組みを指します。
ドライバー不足、2024年問題、CO₂排出量削減、さらにはSDGsやBCP(事業継続計画)といった社会的課題が浮き彫りになる中で、「なぜ今、モーダルシフトなのか?」と疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、モーダルシフトの意味や語源から、必要とされる理由、進まない背景、導入メリット、具体的な企業事例に至るまで、初心者でもわかりやすく解説します。
今後の物流戦略や業界トレンドを押さえるうえで、ぜひ最後までお読みください。
目次
モーダルシフトとは?意味と語源を簡単に解説

「モーダルシフト」という言葉を耳にする機会が増えたけれど、正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。
物流や輸送の現場に関わる人はもちろん、製造・小売など幅広い業界で重要性が増しているこの概念は、今後の持続可能な物流の鍵とも言えます。
ここでは、モーダルシフトの意味や語源をわかりやすく解説し、なぜ今それが注目されているのかを明らかにしていきます。
モーダルシフトとは簡単に
モーダルシフトとは、貨物輸送において主にトラック(自動車)で行っていた輸送を、鉄道や船舶といった環境負荷の低い輸送手段へ切り替えることを指します。
英語では “modal shift” と書き、「輸送手段(モード)の転換」という意味です。
例えば、従来は長距離をトラックで運んでいた荷物を、主要都市間は鉄道で運び、ラストワンマイルだけをトラックで配送するなど、複数の輸送モードを使い分ける輸送スタイルがモーダルシフトです。
語源と物流における意味
「モーダル(modal)」は「輸送手段」や「交通モード」を意味し、「シフト(shift)」は「移行・変更」を意味します。
つまり、「モーダルシフト」は輸送方法を変更することを直訳した表現です。
この概念は元々、環境対策やインフラ活用の最適化を目的に欧米で広まったもので、日本でも地球温暖化対策や労働環境の是正といった文脈で導入が進んできました。
物流においては、「単一モード依存(とくにトラック)」からの脱却を意味し、より効率的かつ持続可能な物流体制の構築を目的とした施策です。
なぜ今、モーダルシフトが注目されているのか
モーダルシフトが強く注目される背景には、以下のような複数の社会的課題があります。
- 物流の2024年問題
ドライバーの時間外労働規制が強化され、長距離輸送が難しくなったことで、輸送力の補完が求められています。 - 地球温暖化とCO₂削減の必要性
運送業界のCO₂排出は全産業の中でも大きな割合を占めており、鉄道や船舶への転換が環境対策として注目されています。 - 人手不足の深刻化
特に若手ドライバーの確保が困難であり、トラックに過度に依存した物流構造の見直しが必要とされています。 - サステナブル経営やESG対応
環境・社会・ガバナンスを重視する企業経営において、モーダルシフトは企業価値向上の一環としても重要視されています。
- モーダルシフトは“脱トラック依存”の第一歩
モーダルシフトとは、「環境に優しく、効率的な輸送への転換」を意味する言葉です。
トラック中心の輸送から鉄道・船舶を活用した多様な輸送手段への切り替えは、物流業界全体の未来を左右する大きな課題です。
ただの“用語”ではなく、ドライバー不足や環境問題など日本の物流が抱える本質的な課題と深く関わるものとして、今こそ多くの企業がその必要性を再認識するタイミングといえるでしょう。
モーダルシフトが必要とされる理由
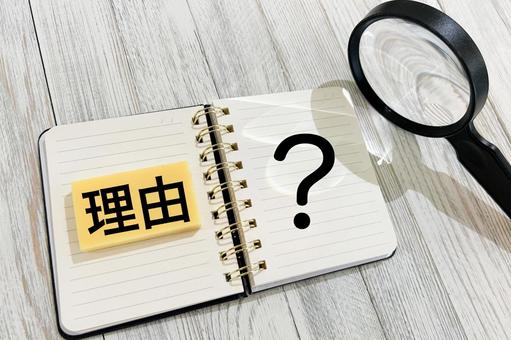
「モーダルシフト」という言葉が注目される背景には、物流業界が直面している人手不足や環境問題などの複雑な課題があります。
従来の輸送方式だけでは立ち行かなくなってきている中、トラック依存からの脱却は避けられない流れとなっています。
ここでは、なぜ今モーダルシフトが必要とされているのか、その4つの主要な理由を解説します。
物流の2024年問題とドライバー不足
2024年4月から適用された働き方改革関連法により、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が設けられました。
これにより、長距離輸送の担い手が減少し、配達の遅延や物流網の逼迫が現実のものとなりつつあります。
特に地方や長距離輸送を支えていた中高年層のドライバーの引退が加速しており、若年層の新規参入も不足。
このような状況下で、鉄道や船舶といった代替輸送手段に物流の一部を移行するモーダルシフトは、持続可能な輸送体制の再構築に不可欠な施策となっています。
関連記事
物流2024年問題とは?トラック運転手不足が運送業界に与える本当の影響
地球温暖化対策としてのモーダルシフト
トラック輸送は、二酸化炭素(CO₂)の排出量が高いという大きな課題を抱えています。
経済産業省のデータによれば、貨物輸送全体のCO₂排出量の約9割以上がトラック由来です。
これに対し、鉄道はトラックの約7分の1、船舶は約5分の1のCO₂排出量で輸送が可能とされています。
環境配慮型物流を目指すうえで、モーダルシフトは最も効果的な手段のひとつです。
SDGs・脱炭素社会への対応
モーダルシフトは、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)にも合致しています。
特に「目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう」「目標13:気候変動に具体的な対策を」の実現に直結する取り組みです。
また、日本政府も「2050年カーボンニュートラル宣言」を掲げており、企業にも環境配慮経営が強く求められています。
トラックから鉄道・船舶へとモードを転換することは、企業の脱炭素経営の実践例としても高く評価されます。
災害時の輸送手段分散(BCP観点)
地震・台風・豪雨といった自然災害が多発する日本では、物流が寸断されるリスクも高まっています。
たとえば、特定の道路が被災した場合、トラック輸送に頼っていると代替ルートが確保できず、物資供給が途絶する恐れがあります。
その点、モーダルシフトにより鉄道や船舶を含む複数モードの併用が進めば、万が一の事態にも柔軟に対応可能です。
企業のBCP(事業継続計画)としても有効な手段といえるでしょう。
▽なぜ今モーダルシフトが必要なのか
モーダルシフトが求められる背景には、物流の危機と社会の変化があります。
ドライバー不足・環境問題・災害リスク・ESG経営といった多角的な課題に対応するには、単なるコスト優先ではない“次世代の輸送戦略”が不可欠です。
今こそモーダルシフトを検討することは、企業価値の向上と社会的責任の両立につながる一歩となるでしょう。
モーダルシフトのメリット

モーダルシフトは「トラック輸送から鉄道や船舶などへの転換」を意味するだけではなく、物流の構造改革や企業経営の質を高める手段としても注目されています。
ここでは、モーダルシフトを導入することで得られる4つの大きなメリットを解説します。
CO₂排出量削減による環境負荷の低減
トラック輸送に比べて、鉄道は約1/7、船舶は約1/5のCO₂排出量で運搬が可能です。
たとえば、トラックで1トンの荷物を100km運んだ場合、排出されるCO₂量は鉄道の約7倍にのぼります。
企業が輸送手段を見直すだけで、環境に与えるインパクトを大幅に軽減できるのは大きな利点です。
また、国際的な環境規制の強化や脱炭素社会への流れを受け、CO₂排出削減はもはや企業の選択ではなく「責務」となりつつあります。
モーダルシフトは、その即効性のある対策のひとつといえるでしょう。
ドライバー不足の解消と労務改善
トラック輸送に依存する現在の物流構造では、ドライバー不足が深刻な課題となっています。
特に2024年問題以降、拘束時間・時間外労働の上限規制により、長距離輸送の担い手が減り、慢性的な人手不足が続いています。
モーダルシフトにより、中距離〜長距離区間を鉄道や船舶でカバーすれば、トラックドライバーは短距離・地場配送に専念できるようになり、労働時間や負担の大幅な軽減が可能です。
結果として、離職率の低下や新規採用の促進にもつながり、企業としての労働環境改善にも寄与します。
長距離輸送コストの最適化
モーダルシフトは環境だけでなく、コスト面でも有利な場合があります。
特に大量輸送や定期ルートにおいては、鉄道や船舶の方がトラックより1kmあたりの輸送単価が安くなる傾向があります。
例えば、定期便や大口輸送では鉄道コンテナを活用することで、1輸送あたりのコストを30%以上削減できた事例もあります。
もちろん、積み替えや拠点整備といった初期費用は発生しますが、中長期的な視点ではコスト最適化につながる点は大きなメリットです。
企業のESG・CSR評価の向上
昨今の投資・調達活動では、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)への対応が問われるようになっています。
モーダルシフトを実施することで、環境配慮型企業としての評価が高まり、資金調達や取引先選定において有利に働くケースも増えています。
また、CSR(企業の社会的責任)の観点からも、持続可能な物流へのシフトは企業の社会的信頼を高める行動として評価されます。
特にBtoB取引の多い企業や輸出入業務を行う事業者にとっては、海外の環境基準にも対応する意味でも重要なポイントです。
▽モーダルシフトは企業にも社会にも“持続性”をもたらす
モーダルシフトは単なる輸送手段の変更ではなく、環境対応・人材確保・コスト削減・企業価値向上といった複数の課題を一度に解決する手段として注目されています。
一歩踏み出すことで、社会課題への対応と企業利益の両立が可能となるのです。
モーダルシフトが進まない理由と課題

CO₂削減やドライバー不足対策として注目されているモーダルシフトですが、現場ではなかなか普及が進んでいないのが実情です。
環境やコスト面でのメリットがある一方で、物流企業や荷主にとっては運用上のハードルも多く存在しています。
ここでは、モーダルシフトが思うように進まない代表的な要因と、それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。
リードタイムの増加と納期の不安定さ
鉄道や船舶を使った輸送は、トラックに比べて出発時刻や到着時刻が固定化されているため、柔軟な対応が難しくなります。
特に鉄道輸送では、積み込みから配達までに中1〜2日程度のタイムラグが発生することもあり、トラックのような即日配達には向きません。
また、土日祝の運行休止や積み替え地点での停滞などにより、納期が不安定になりやすく、“Just In Time”を重視する業種では導入に慎重にならざるを得ません。
積み替えの手間と貨物破損リスク
モーダルシフトでは、トラック⇄鉄道・船舶間の積み替え作業が不可欠です。
この過程で時間と労力がかかるだけでなく、積み荷の破損や紛失のリスクも高まります。
とくに精密機器や割れ物などを扱う企業では、1回の積み替えでも大きなストレスや事故の原因となりうるため、輸送品質の担保が難しい点が大きな障壁です。
天候や災害に左右されやすい輸送手段
鉄道や船舶は、トラックよりも天候や自然災害の影響を受けやすい輸送モードです。
例えば台風や大雪があれば鉄道は運休、船便は遅延または欠航になり、物流の停止リスクが現実的に高くなります。
これにより、納期の遅延や顧客からの信頼低下が懸念され、不測の事態への対応力の低さが企業にとっては大きなネックになります。
インフラ不足・港湾・鉄道の対応力の限界
モーダルシフトを実現するには、鉄道貨物駅や港湾ターミナルの物流対応力が重要です。
しかし、地方や中小都市では鉄道貨物駅自体が存在しない、または運行本数が限られているケースもあり、対応できるインフラが十分でないのが現状です。
また、鉄道会社や港湾事業者の人的リソースや機材の制約から、繁忙期には輸送予約が取れないといった問題も生じており、安定した輸送体制の構築が課題となっています。
▽課題を超えるには“業界全体の改革”がカギ
モーダルシフトは理想的な仕組みではあるものの、実際の導入には多くの現実的な壁があります。
リードタイム、積み替えの手間、インフラの脆弱性など、それぞれの課題に対しては企業単位での工夫と、国・自治体によるインフラ整備支援が両輪となる対応が求められます。
持続可能な物流を目指すには、「できない理由」より「どうすればできるか」を業界全体で考える姿勢が不可欠です。
モーダルシフトを支援する国や自治体の取り組み

モーダルシフトの普及が進まない原因のひとつに、インフラや制度の整備不足があります。
これに対して国や自治体では、企業の取り組みを後押しするさまざまな補助金や支援策を用意し、物流の脱炭素化・効率化を促しています。
ここでは代表的な制度や事業の内容を解説し、実際に活用されている支援策の概要を紹介します。
モーダルシフト等推進事業と補助金制度
国土交通省では、企業が鉄道・海運への輸送切り替えを実施する際の初期コストや設備投資に対し補助金を支給しています。
代表的な支援制度が「モーダルシフト等推進事業補助金」です。
この補助金では以下のような取り組みに対して支援が行われます。
- 鉄道・船舶輸送への切り替えによる実証実験
- 物流センター・倉庫の集約や拠点の最適化
- 複数荷主による共同輸送の実現に向けた設備投資
支給額は最大で費用の1/2〜2/3まで補助されるケースもあり、中小企業でも導入しやすい制度設計となっています。
国交省「物流革新緊急パッケージ」とは
2023年に国土交通省が発表した「物流革新緊急パッケージ」は、2024年問題に対応するための政策的ロードマップです。
その中でもモーダルシフトは、人手不足・長時間労働是正・環境配慮をすべて同時に達成する手段として、重点施策に位置づけられています。
具体的な取り組みには以下が含まれます。
- 鉄道会社・海運事業者との連携促進
- デジタル化による物流情報の見える化
- 規制緩和による輸送手段間のスムーズな接続
このパッケージは単なる補助金制度だけでなく、制度改革・企業間調整・インフラ支援の総合政策として設計されており、官民連携によるモーダルシフトの基盤づくりが進められています。
地域連携による共同輸送・中継輸送の支援
モーダルシフトは個社単独で完結することが難しいため、地域ぐるみでの共同輸送体制の構築も進められています。
たとえば、自治体主導で以下のような取り組みが行われています。
- 地元企業同士の荷物の混載(ラウンド輸送)
- トラック運転の中継輸送(バトンタッチ方式)
- 鉄道貨物駅へのアクセス改善(道路整備やシャトル便補助)
これらの仕組みは特に地方の中小企業や物流企業にとって導入ハードルを下げる効果があり、地域経済の活性化と環境対応を両立する事例として注目されています。
▽官民連携がモーダルシフト成功の鍵
モーダルシフトを促進するには、企業努力だけでなく制度・資金・インフラの後押しが不可欠です。
国や自治体による補助金や支援施策を活用することで、中小企業でもリスクを抑えてモーダルシフトに取り組むことが可能となります。
今後は、より柔軟な制度運用と多様な連携モデルの構築を通じて、「運べない時代」に対応する持続可能な物流体制づくりが求められていくでしょう。
モーダルシフトを導入している企業事例

モーダルシフトはまだ一般化しているとは言えませんが、先進的な企業はすでに実践し、成果を上げています。
特に鉄道や海上輸送を活用することで、環境負荷の低減やコスト削減を実現している企業が増えつつあります。
ここでは、代表的な導入企業の事例を3つ紹介し、具体的な効果や工夫について解説します。
鉄道活用事例|ネスレ日本
ネスレ日本は、東北・関東から関西エリアへの製品輸送において、従来のトラック輸送から鉄道輸送へと切り替えるモーダルシフトを実施しました。
この取り組みにより、年間で約2,300トンのCO₂排出量削減を達成。さらに、トラックドライバーの労働時間短縮や労務コスト削減といった副次的な効果も確認されています。
ネスレはこの実績から、環境配慮と労働環境改善の両立に成功した事例として、業界内外から注目を集めています。
海上輸送活用事例|味の素・大手飲料メーカー
味の素は、九州工場で製造された製品を関東の物流拠点へ配送する際に、フェリーによる海上輸送を導入しました。
同様に、大手飲料メーカーも北海道や四国からの原料輸送にフェリー便を利用し、トラック長距離運行の回避を図っています。
これらの事例では、以下のようなメリットが報告されています。
- 長距離区間のトラック運行を削減し、ドライバー不足リスクを軽減
- フェリー内での休息時間を運転時間にカウントしないため、拘束時間の短縮
- CO₂排出量の削減により、環境認証取得やESG評価にプラス
海上輸送は天候の影響を受けやすいという課題があるものの、輸送コスト・環境配慮の両立を図れる手段として注目されています。
共同輸送によるコスト削減例
複数企業が手を組み、同じ配送ルートや集配拠点をシェアする共同輸送も、モーダルシフトと並行して活用されています。
たとえば食品メーカーと日用品メーカーが、鉄道コンテナを共同で利用し関東から関西へ混載輸送することで、以下の成果を上げました。
- 積載率の向上により、1社あたりの物流コストを約15%削減
- 輸送頻度を維持しながらも、トラック使用台数を年間で約30台削減
- 輸送過程の可視化により、輸送中の品質管理や納期対応力も向上
共同輸送の鍵は、「情報共有の仕組みづくり」と「拠点やスケジュールのすり合わせ」です。
物流の効率化とCO₂削減の双方を達成する新しい連携モデルとして、今後ますます期待が寄せられています。
▽実例に学ぶ、モーダルシフト成功のヒント
モーダルシフトの導入は決して大手企業だけのものではありません。
鉄道・船舶・共同輸送などの選択肢を柔軟に組み合わせることで、環境への配慮と物流コストの削減を同時に実現することが可能です。
成功企業の共通点は、以下の3つに集約されます。
- 綿密な輸送計画とスケジュール管理
- 荷主間の連携や情報共有の仕組み
- 補助金制度や国の支援の積極的活用
これらを参考に、自社に合ったモーダルシフト戦略を模索していくことが今後の鍵となるでしょう。
モーダルシフトを導入する際のポイント

モーダルシフトは、単なる輸送手段の切り替えではなく、企業の物流全体の見直しが必要な戦略的アプローチです。
導入を成功させるには、「輸送方法を変えるだけ」では不十分で、組織全体の調整力や在庫管理体制、倉庫連携など複数の要素が求められます。
ここでは、モーダルシフトを実践する際に押さえておきたい4つの重要なポイントを具体的に解説します。
荷主企業側の物流戦略と調整力
モーダルシフトを進めるには、まず荷主企業自身が主導権を持ち、物流戦略を明確に描く必要があります。
- 「何を、いつ、どのモードで送るのか」
- 「納品リードタイムはどこまで許容できるのか」
- 「受け取り側とどう調整するか」
といった項目を事前に洗い出し、社内外の関係者との調整力を高めることがカギになります。
とくに、小売業や製造業では、営業部門との納期折衝や在庫リスクの調整が必要不可欠。輸送手段の選定だけでなく、サプライチェーン全体の調和が重要です。
配送ルートの最適化と在庫管理
トラックから鉄道・船舶に切り替えると、リードタイムが長くなる可能性があります。
そのため、モーダルシフト導入時には以下の見直しが求められます。
- 在庫配置の見直し
- リードタイムに応じた追加在庫の確保
- 納品先別のルート最適化
これにより、配送の柔軟性が維持され、安定供給と在庫過剰の両リスクを回避することが可能です。
また、WMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)と連携することで、在庫状況や輸送状況をリアルタイムで把握し、意思決定のスピードを高める効果も期待できます。
倉庫やハブ拠点の活用と連携
モーダルシフトでは、中継拠点となる倉庫やハブ施設の役割が極めて重要です。
とくに、鉄道や船舶輸送では、積み替えのタイミングが増えるため、次の点がポイントとなります。
- 積み替え作業のスムーズさ(設備・人材)
- リードタイムを最小限にする配置計画
- ハブ間の距離と交通アクセスの検討
企業によっては、自社倉庫を中継拠点として活用するだけでなく、3PL企業や物流協業ネットワークと連携し、全国の倉庫網を共有するケースもあります。
このように、倉庫を“保管の場”から“輸送連携の拠点”へと再定義する視点が求められます。
モーダルミックス(複数手段の組合せ)の検討
モーダルシフトを成功させている企業の多くは、1つの輸送手段に依存するのではなく、複数のモードを組み合わせて最適化(モーダルミックス)しています。
たとえば:
- 鉄道輸送+ラストワンマイル配送(トラック)
- フェリー輸送+中継拠点配送
- 都市圏はトラック/長距離は鉄道 or 船舶
というように、目的地・時間・貨物の特性に応じて最適な組み合わせを設計することが重要です。
これにより、柔軟な物流設計が可能になり、BCP(事業継続計画)対応やコスト分散にもつながります。
▽モーダルシフト導入の鍵は“全体最適”の視点
モーダルシフトは単なるトラック輸送の代替策ではなく、物流全体を見直す改革の一環です。以下の要素を意識することで、企業として持続可能な輸送体制を構築できます。
- 荷主が主体的に物流設計と調整を担うこと
- 在庫管理とルート設計をセットで最適化すること
- 中継拠点の有効活用でスムーズな連携を築くこと
- 複数モードの活用で安定性と柔軟性を両立すること
全体最適の視点を持ち、テクノロジーやパートナー企業との連携を積極的に進めることが、モーダルシフト成功への第一歩となるでしょう。
物流の未来を変える挑戦“モーダルシフト2.0”という考え方

これまでのモーダルシフトは、「環境にやさしい輸送手段への切り替え」という位置づけでした。
しかし、時代は“輸送の効率化”から“ロジスティクス全体の再設計”へと動き出しています。
今、物流業界が注目するのが、次世代型の取り組み「モーダルシフト2.0」。
単なる輸送手段の変更ではなく、戦略的なサプライチェーン構築・テクノロジーの活用・柔軟な対応力の強化など、物流を企業競争力の源泉へと進化させる考え方です。
単なる輸送手段の切り替えから“戦略的ロジスティクス”へ
モーダルシフト2.0は、「トラックから鉄道・船舶へ」という単純な切り替えにとどまらず、企業戦略と結びついたロジスティクス改革を意味します。
以下のような視点が鍵を握ります。
- 物流コストだけでなく、リードタイム・在庫回転率・温室効果ガス削減など多指標の最適化
- サプライチェーン全体を俯瞰し、“どこを・どの手段で・いつ”運ぶかを戦略的に設計
- 営業・製造・販売との連携による全社横断的な意思決定
このように、モーダルシフトはもはや輸送部門だけの課題ではなく、経営レベルでの意思決定が求められるフェーズに突入しています。
モーダルミックスによる柔軟なサプライチェーン構築
従来のように「1つの輸送モードに依存する」形から脱却し、複数の輸送手段を組み合わせて柔軟に対応する“モーダルミックス”が注目されています。
例として、
- 鉄道+トラックによる都市部ラストワンマイル対応
- フェリー+中継倉庫による海上輸送の安定確保
- 平常時は低コスト手段、災害時は代替手段を想定した二重ルート設計
といった多様な物流構成が、新時代のBCP(事業継続計画)にも直結します。モーダルシフト2.0では、このようなモードの多層的活用が、企業の競争力を高める要素になるのです。
テクノロジーとの融合で実現する次世代物流モデル
モーダルシフト2.0を支える柱のひとつが、AI・IoT・データ解析などのテクノロジーとの融合です。
輸送効率を高め、トラブル時の対応力を上げるだけでなく、次のような効果が期待できます。
- AIによる需要予測で倉庫配置や輸送スケジュールを最適化
- IoTセンサーで貨物の温度・振動・位置をリアルタイム監視
- デジタルツインを活用し、仮想環境で物流モデルをシミュレーション
さらに、脱炭素対応・ESG経営にも直結する指標を可視化できる点も、経営層からの評価を高めています。
もはや「モーダルシフトは現場任せ」ではなく、「テクノロジー活用による企業変革の一部」へと進化しているのです。
▽モーダルシフト2.0は企業の“次の一手”
従来の輸送手段の見直しという枠を超えたモーダルシフト2.0は、企業の持続的成長と社会貢献を両立させる次世代の物流戦略です。
- 輸送の効率化だけでなく、全体最適のロジスティクス設計へ
- 単一モードから脱却し、柔軟性とリスク分散を兼ね備えたモーダルミックスへ
- テクノロジーの融合によって、予測・可視化・自動化の精度を高める
物流を「コスト」から「価値創造の武器」へ変えるチャンスとして、今こそ企業が一歩踏み出すタイミングかもしれません。
モーダルシフト2.0は、持続可能な未来への架け橋となることでしょう。
まとめ|モーダルシフトは“持続可能な物流”の鍵

環境問題と人手不足という二大課題に直面する日本の物流業界において、モーダルシフトは単なる輸送手段の変更を超えた、構造的な解決策として注目を集めています。
本記事ではその全体像を紐解いてきましたが、最後に改めて、なぜモーダルシフトが今後の物流の“鍵”となるのかを整理しましょう。
脱炭素と物流危機への現実的な対策
モーダルシフトは、CO2排出量の削減に直結するだけでなく、2024年問題に代表されるトラックドライバー不足への現実的な解決策としても有効です。
鉄道や船舶といった輸送手段への切り替えによって、少人数でも大量輸送が可能になり、労働環境の改善にもつながります。
また、企業のサステナビリティ戦略の一環としても採用が進んでおり、環境配慮の姿勢が取引先や消費者からの信頼を得る重要な要素となっています。
脱炭素時代において、物流のあり方を見直すことは、企業全体の競争力向上につながるといえるでしょう。
中長期視点で取り組む企業価値向上の一歩
モーダルシフトの導入は、短期的にはコストや手間がかかる場合もありますが、長期的には「持続可能な物流体制の構築」と「企業価値の向上」につながる投資と捉えるべきです。
以下のような効果が中長期で期待できます。
- BCP対策(災害リスク分散)による安定供給体制の構築
- ESG・CSRへの対応による上場企業としての評価向上
- 輸送効率の改善によるコスト最適化
こうした点からも、モーダルシフトは“運輸部門の取り組み”を超えて、経営判断としての価値を持つ戦略的施策だといえるでしょう。
今後の課題と社会全体での取り組みの必要性
もちろん、すべての企業がすぐにモーダルシフトを進められるわけではありません。
鉄道・港湾インフラの未整備、納期やコストの課題、積み替え時のリスクなど、現場レベルの課題も根強く残っています。
しかし、それらを解決するために、以下のような社会全体での支援と連携が不可欠です。
- 国や自治体による補助金制度や法整備の強化
- 荷主・物流会社・行政の三者連携による共同輸送・中継輸送の推進
- インフラ整備と情報共有を支えるIT基盤の構築
個社の努力だけでなく、物流全体を捉えた広い視点でのアプローチが、モーダルシフトの本格普及には必要不可欠です。
モーダルシフトは、今の物流業界が抱える問題を“持続可能性”という視点で乗り越えるためのカギです。
脱炭素・人材不足・災害対策という多くの課題に、ひとつの解を提示するこの取り組みは、単なる流行ではなく、企業の未来を支えるロジスティクス戦略といえるでしょう。
今こそ、目先の効率だけでなく、「将来の安心と信頼」に投資する時期です。
物流の進化が、日本の産業全体を次のステージへと押し上げる一歩となるかもしれません。





